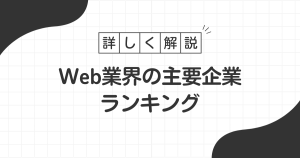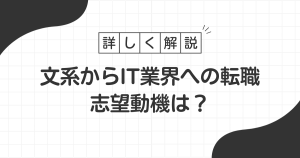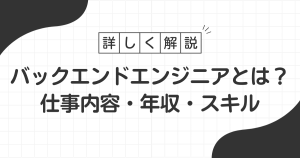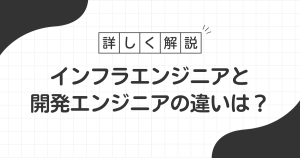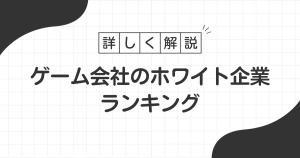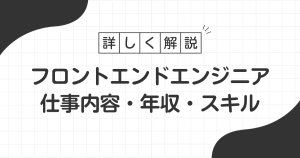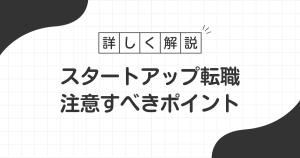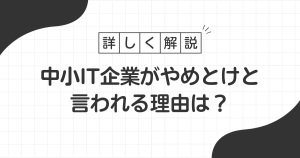プログラミングやIT技術への関心が高まる中で、Webエンジニアを目指す人が増えています。しかし、ネットで検索すると「Webエンジニア やめとけ」という言葉をよく見かけます。
本当にWebエンジニアはやめた方がいい職業なのでしょうか。実際に働いている人たちの声や業界の実情を踏まえて、やめとけと言われる理由と、それでも向いている人の特徴を詳しく解説します。転職を検討している方は、メリットとデメリットの両面を理解した上で判断してください。
Webエンジニアはやめとけと言われる10個の理由
Webエンジニアに対してネガティブな意見が出る背景には、現実的な課題があります。ここでは、実際に現場で働く人たちが感じている10の理由を見ていきましょう。
1. 業務の範囲が広くフルスタック化を求められるから
Webエンジニアは、フロントエンドからバックエンドまで幅広い技術領域をカバーする必要があります。HTML、CSS、JavaScriptといったフロントエンド技術だけでなく、サーバーサイドの言語やデータベース、インフラ周りの知識まで求められることが多いです。
特に中小企業やスタートアップでは、限られた人員でプロジェクトを進めるため、一人で何役もこなさなければなりません。デザイナーの作業やディレクションまで任されるケースもあり、専門性を深めることが難しくなります。
フルスタック化により、表面的な知識は身につくものの、特定分野での深い専門性を磨く時間が取れないという問題もあります。結果として、市場価値の向上が難しくなる可能性があります。
2. 常にスピード感を求められて激務になりやすいから
Web業界は変化が激しく、競合他社に先駆けてサービスをリリースする必要があります。そのため、短期間での開発が求められ、残業や休日出勤が常態化している企業も少なくありません。
特にベンチャー企業では、限られた資金と時間の中で成果を出すプレッシャーが強く、働き方改革が進んでいない職場も存在します。リリース前の追い込み期間では、徹夜作業が続くこともあります。
また、バグ修正やサーバーダウンなどの緊急対応では、深夜や休日でも呼び出される可能性があります。ワークライフバランスを重視する人には厳しい環境と言えるでしょう。
3. 薄利多売のビジネスモデルで給料が上がりにくいから
Web制作会社の多くは、受託開発をメインとしており、価格競争が激しい業界です。クライアントからの値下げ要求も多く、利益率の低いプロジェクトを数多くこなす薄利多売の構造になっています。
特にコーポレートサイトやECサイトの制作では、テンプレートを使った低価格サービスが増えており、付加価値の低い案件では単価が下がり続けています。結果として、従業員の給与水準も他のIT職種と比べて低めに設定されがちです。
経験を積んでスキルが向上しても、会社の売上構造が変わらない限り、大幅な昇給は期待できません。個人のスキルアップが直接的に収入増に結びつかない点が、やめとけと言われる理由の一つです。
4. 継続的な学習が必要で新技術を追い続けなければならないから
Web技術の進歩は非常に速く、新しいフレームワークやライブラリが次々と登場します。数年前に主流だった技術が急速に時代遅れになることも珍しくありません。
例えば、JavaScriptのフレームワークだけでも、jQuery、Angular、React、Vueなど様々な選択肢があり、それぞれに学習コストがかかります。さらに、新しいバージョンのリリースにより、既存の知識がすぐに古くなってしまいます。
仕事終わりや休日を使って勉強することが当たり前とされる風潮もあり、プライベートの時間を犠牲にしてまで学習を続けることに疲れを感じる人も多いです。常に学び続けることができない人は、市場から取り残される可能性があります。
5. 競争が激化しており飽和状態に近づいているから
プログラミングスクールの普及により、Webエンジニアの数は急激に増加しています。短期間でスキルを身につけて転職を目指す人が多く、特に未経験者向けのポジションでは激しい競争が起きています。
さらに、海外のエンジニアとの競争も避けられません。リモートワークの普及により、人件費の安い国のエンジニアに仕事を発注するケースが増えており、国内のWebエンジニアの仕事が奪われる可能性もあります。
経験の浅いエンジニアにとっては、差別化が難しく、価格競争に巻き込まれやすい状況です。高いスキルや専門性を持たない限り、安定した収入を得ることが困難になっています。
6. キャリア形成の道筋が見えにくいから
Webエンジニアのキャリアパスは、他の職種と比べて明確ではありません。技術を極めてスペシャリストになるか、マネジメント側に回るかの選択肢はありますが、具体的にどのようなスキルを身につければよいか分からない人も多いです。
特に中小企業では、先輩エンジニアの数が少なく、ロールモデルとなる人材がいません。どのような経験を積めば市場価値が上がるのか、将来的にどのようなポジションを目指せばよいのかが見えにくい状況です。
また、技術職としてのキャリアアップには、継続的なスキルアップが必要ですが、年齢を重ねるとともに新しい技術への適応が難しくなる場合もあります。長期的なキャリア設計が立てにくいことが不安要素となっています。
7. ベンチャー企業が多く福利厚生が不十分だから
Web業界には、設立間もないベンチャー企業やスタートアップが多く、大手企業と比べて福利厚生が充実していない傾向があります。退職金制度がない、有給取得率が低い、健康診断が年1回のみといった状況も珍しくありません。
特に創業期の企業では、社会保険の加入すら怪しい場合もあり、将来的な保障に不安を感じる人も多いです。また、オフィス環境が整っていない、設備投資が不十分といった問題もあります。
安定した雇用環境を求める人にとっては、ベンチャー企業特有の不安定さがデメリットとなります。会社の経営状況によっては、突然の倒産やリストラのリスクも考慮しなければなりません。
8. AI技術の進化で将来性が不安視されているから
近年のAI技術の発展により、Webエンジニアの仕事の一部が自動化される可能性が指摘されています。コード生成AIやノーコード・ローコード開発ツールの普及により、簡単なWebサイト制作は専門知識がなくてもできるようになりつつあります。
特に、テンプレートベースのサイト制作や単純なコーディング作業は、AIに置き換わる可能性が高いとされています。これにより、低スキルのWebエンジニアの需要は減少する可能性があります。
ただし、複雑なシステム設計や高度な技術を要する開発では、まだ人間のエンジニアが必要とされています。将来的にAIと共存していくためには、より高度なスキルを身につける必要があります。
9. 退職金がない企業が多いから
Web業界の多くの企業、特にベンチャー企業では退職金制度がありません。これは、長期雇用を前提とした従来の日本企業の慣習とは異なる文化のためです。
転職が当たり前とされるWeb業界では、長期間同じ会社に勤める人が少なく、企業側も退職金制度を設けるメリットが少ないと考えています。そのため、老後の資金は自分で準備する必要があります。
退職金がないことで、将来への不安を感じる人も多く、特に家族を養う立場の人にとっては大きなデメリットとなります。個人型確定拠出年金(iDeCo)などの制度を活用した自助努力が求められます。
10. 特別な技術が身につかず市場価値が上がりにくいから
Webエンジニアの仕事は、既存の技術やフレームワークを組み合わせることが多く、独自性の高いスキルを身につけることが困難です。多くの人が同じような技術を使って同じような仕事をしているため、差別化が難しい状況です。
特に、WordPressのテンプレート制作やHTML・CSSのコーディングなど、エントリーレベルの業務では、代替可能な人材が多く存在します。このような業務では、経験年数に関係なく単価が上がりにくい傾向があります。
市場価値を高めるためには、特定の分野で深い専門性を身につけるか、技術以外のスキル(マネジメント、営業、企画など)を組み合わせる必要があります。しかし、日常業務に追われて、そのような時間を確保することが難しいのが現実です。
Webエンジニアに向いている人の7つの特徴
やめとけと言われる理由がある一方で、Webエンジニアとして成功している人たちには共通の特徴があります。これらの特徴を持っている人は、困難な状況でも乗り越えて成長できる可能性が高いです。
新しい技術を学ぶことが好きな人
Web技術の進歩は非常に速く、常に新しい知識を吸収する必要があります。これを負担に感じるのではなく、楽しみながら学習できる人は、Webエンジニアに向いています。
新しいフレームワークやライブラリが登場したときに、積極的に試してみたくなる好奇心旺盛な人は、業界の変化についていくことができます。また、学習すること自体にやりがいを感じられる人は、継続的なスキルアップが苦になりません。
技術書を読んだり、オンライン講座を受講したり、勉強会に参加したりすることを楽しめる人は、自然とスキルが向上し、市場価値も高まっていきます。学習習慣が身についている人は、長期的に成功する可能性が高いです。
論理的思考力がある人
プログラミングは、論理的に物事を組み立てて問題を解決する作業です。複雑な要件を整理し、効率的なアルゴリズムを考え、バグの原因を特定するなど、すべて論理的思考力が必要になります。
数学的な思考が得意で、物事を段階的に分解して考えることができる人は、プログラミングに向いています。また、因果関係を正しく理解し、問題の根本原因を見つけることができる人は、高品質なコードを書くことができます。
論理的思考力は、技術的な問題解決だけでなく、プロジェクト管理や要件定義の場面でも重要です。クライアントの要望を整理し、実現可能な形に落とし込む能力は、エンジニアとしての価値を高めます。
コミュニケーション能力が高い人
Webエンジニアは一人で黙々と作業するイメージがありますが、実際にはチームでの協力が不可欠です。デザイナー、ディレクター、クライアントと円滑にコミュニケーションを取れる人は、プロジェクトを成功に導くことができます。
技術的な内容を非エンジニアにも分かりやすく説明できる人は、重宝されます。また、チームメンバーとの意見交換や課題の共有ができる人は、より良いサービスを作り上げることができます。
コードレビューや技術相談など、エンジニア同士のコミュニケーションも重要です。建設的な議論ができる人は、チーム全体のスキルアップに貢献し、自分自身も成長することができます。
地道で粘り強い作業が苦にならない人
プログラミングには、バグの修正やコードの最適化など、地味で時間のかかる作業が多く含まれます。一つの問題を解決するために、何時間も試行錯誤を続けることも珍しくありません。
このような作業を苦痛に感じず、むしろ問題解決のプロセスを楽しめる人は、Webエンジニアに向いています。小さな改善を積み重ねることで、より良いサービスが作れることを理解している人は、長期的に成果を出すことができます。
また、細かいテストやデバッグ作業を丁寧に行える人は、品質の高いシステムを構築できます。急がず慌てず、一つずつ確実に問題を解決していく姿勢が重要です。
効率的に物事を進められる人
Web開発では、限られた時間とリソースの中で最大の成果を出すことが求められます。優先順位をつけて作業を進めたり、自動化できる部分を見つけたりする能力は、非常に重要です。
既存のライブラリやフレームワークを適切に活用し、車輪の再発明を避けることができる人は、効率的に開発を進められます。また、コードの再利用性を考慮して設計できる人は、将来的な保守コストを削減できます。
時間管理能力があり、スケジュール通りにプロジェクトを進められる人は、クライアントからの信頼を得ることができます。効率性と品質のバランスを取りながら作業できる人は、エンジニアとして高く評価されます。
臨機応変に対応できる人
Web開発では、仕様変更や急な修正依頼が頻繁に発生します。完璧な計画を立てても、途中で方向性が変わることは日常茶飯事です。このような状況に柔軟に対応できる人は、現場で重宝されます。
新しい技術要件が追加されたときに、素早く学習して対応できる適応力も重要です。また、複数のプロジェクトを並行して進める場合は、優先順位を判断して作業を切り替える能力も必要になります。
予想外の問題が発生したときに、代替案を考えて解決策を提示できる人は、チームの頼れる存在となります。柔軟性と創造性を持って課題に取り組める人は、困難な状況でも成果を出すことができます。
細部までこだわって作業ができる人
Webサイトやアプリケーションは、ユーザーが直接触れるものです。小さなバグやデザインの不具合でも、ユーザー体験を大きく損なう可能性があります。そのため、細部まで丁寧に作り込める人は、高品質なサービスを提供できます。
コードの可読性や保守性にこだわり、将来の開発者が理解しやすいプログラムを書ける人は、長期的にプロジェクトに貢献できます。また、パフォーマンスやセキュリティに配慮した実装ができる人は、技術的な価値を提供できます。
ユーザー目線でサービスを検証し、使いやすさを追求できる人は、より良いプロダクトを作ることができます。妥協せずに品質を追求する姿勢は、プロフェッショナルなエンジニアとしての基本です。
それでもWebエンジニアを目指すべき3つの理由
やめとけと言われる理由があるものの、Webエンジニアには他の職種にはない魅力的な側面もあります。特に以下の3点は、現代の働き方において大きなメリットとなります。
リモートワークが普及していて働き方に自由度がある
Webエンジニアは、パソコンとインターネット環境があれば作業できるため、リモートワークに最も適した職種の一つです。新型コロナウイルスの影響で多くの企業がリモートワークを導入し、この流れは今後も続くと予想されます。
通勤時間がなくなることで、プライベートの時間を有効活用できます。また、住む場所の制約がなくなるため、家賃の安い地方に住みながら都市部の企業で働くことも可能です。
フレックスタイム制を導入している企業も多く、自分のライフスタイルに合わせて労働時間を調整できます。子育てや介護などの事情がある人にとっても、働きやすい環境を作りやすい職種です。
需要が高く転職しやすい職種である
DXの推進により、多くの企業がWebサービスの開発や既存システムのモダン化を進めています。そのため、Webエンジニアの需要は継続的に高い状況が続いています。
経験者はもちろん、未経験者でも研修制度が充実している企業が増えており、キャリアチェンジのハードルが低くなっています。また、スキルがあれば年齢に関係なく転職できる可能性があります。
転職市場が活発なため、スキルアップに応じて条件の良い会社に移ることができます。同じ会社に長期間勤めなくても、転職を通じてキャリアアップを図ることが可能です。
副業やフリーランスとしての可能性が広がる
Webエンジニアのスキルは、副業やフリーランスとして活用しやすい特徴があります。クラウドソーシングサイトには多くの案件があり、在宅で作業できるものが大部分を占めています。
スキルと実績があれば、会社員の給与を上回る収入を得ることも可能です。特に、特定の分野に特化した専門性があれば、高単価の案件を受注できる可能性があります。
また、自分でWebサービスを開発して収益化することも可能です。アイデアと技術力があれば、個人でもビジネスを立ち上げることができる分野です。経済的な自立や独立を目指す人にとって、魅力的な選択肢となります。
まとめ
Webエンジニアをやめとけと言われる理由には、業務範囲の広さ、激務になりやすい環境、給与の上がりにくさなどの現実的な課題があります。継続的な学習が必要で、競争も激化しているため、向き不向きがはっきりと分かれる職種と言えるでしょう。
一方で、新しい技術を学ぶことが好きで、論理的思考力があり、コミュニケーション能力の高い人には向いている職種です。また、リモートワークの普及や転職のしやすさ、副業・フリーランスとしての可能性など、現代の働き方に適した魅力もあります。
Webエンジニアを目指すかどうかは、自分の性格や価値観、将来のビジョンと照らし合わせて判断することが大切です。困難な面もありますが、適性がある人にとっては充実したキャリアを築ける可能性の高い職種です。転職を検討している方は、メリットとデメリットを十分に理解した上で、慎重に決断してください。